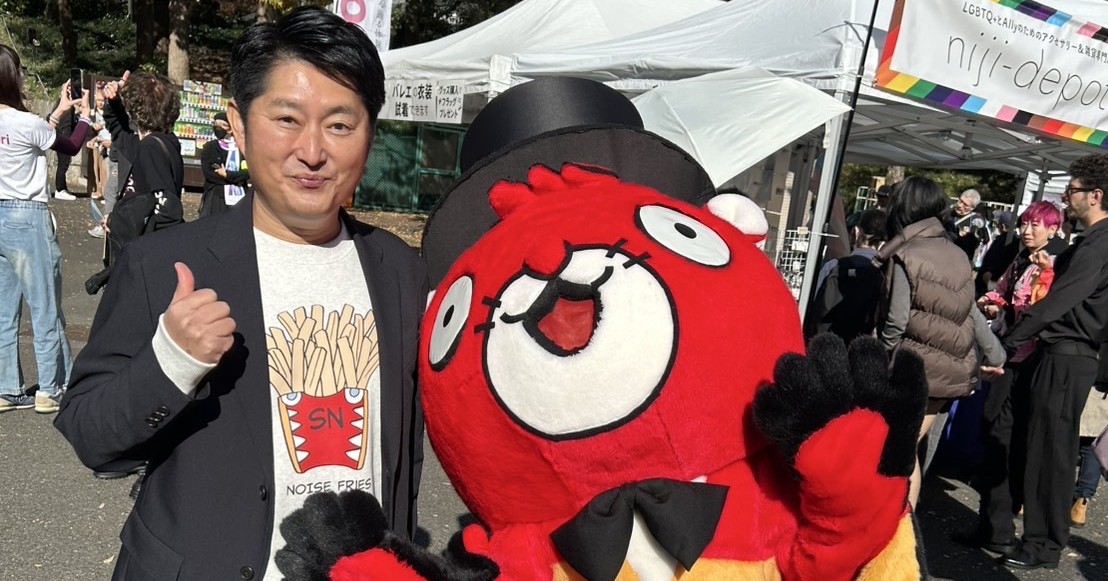ケア労働としてのセックスワーカー論
令和の家父長制として
11月11日の衆院予算委員会で、高市早苗首相が買春処罰法に前向きな答弁をして以来、あれだけ高市氏を口汚く罵っていたフェミニストたちは一変し、同調する言動を始めました。
まるで戦時下の国防婦人会やキリスト教矯風会を彷彿とさせる言説に、「なぜ彼女たちは一周回って保守と手を繋いでしまったのか?」と嘆き悲しむ声がネットには溢れました。
無料で『松浦大悟のニュースレター』をメール配信します。コンテンツを見逃さず、読者限定記事も受け取れます。
かつて、フェミニズムには二つの支柱がありました。
一つは「平等」、もう一つは「自由」です。
「平等」とは、人間としての権利を男性とイコールにしていくということ。
「自由」とは女性の解放のことであり、そこには男性視線に縛られない性の自由も含まれます。
家父長制のもとで自分の身体さえ自由にできなかった女性たちは、「私の体は私のもの。父親のものでも夫のものでもない」と声をあげたのです。
それが「性の自己決定」との考えに繋がっていきます。
ところが近年、フェミニズムにおいては権利の平等ばかりが主張され、「性からの自由、性への自由」を求める議論は避けられる傾向にあるのです。
こうした歴史を踏まえ、私は以下の考察をXにアップしました。
いま80歳90歳くらいの女性たちは、夫婦間のセックスを「夜のお勤め」と呼んでいた。
当時AVはなかったので、多くの男性たちは前戯というものを知らず、女性器が濡れてもいないのに挿入していた。
女性たちはそれが痛くてたまらず、毎日陰鬱な気持ちで夜を迎えていた。
上野千鶴子さんは、そんな一世代前の女たちの怨念を背負って登場した。
フェミニストが作ったセクハラ概念が過剰になってしまったのも、ある意味わからなくはない。
「男の身勝手さ」「女性との実感の違い」を男性に知らしめる役割を果たしたのは事実だが、行きすぎたセクハラ概念は、男たちを性から退却させた。
いまや学校や職場で女性に声をかける男性はほとんどいない。
もしセクハラだと訴えられたら一生を棒に振るからだ。
その結果、何が起こったのか。
体を触ってもらえなくなった女性たちは人肌が恋しくなり、女性用風俗に殺到しているのである。
こうした現象をこそ朝日新聞は分析すべきだろう。
朝日新聞の論理でいうなら、ママ活、女風、ホスト狂いの「男を買う女」たちは性加害者に他ならない。
だが、本当にそうなのか?
真に論じるべき課題はそこにある。